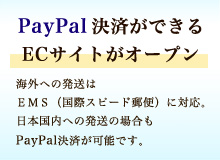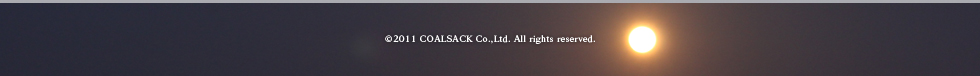<詩作品>
雷 鳴
昔、子どもの頃雷様は非常に恐ろしいものでした。夏、もくもくと湧き上がる雲を見つめ、やがて夕立が来るのを予感していました。そんな暑い中でも石けり、かくれんぼ、鬼ごっこと子どもたちの遊ぶ種は尽きません。大尽様の家の周りは子どもたちの歓声で満ち溢れていました。俄かに空が真っ黒になると歓声はやみ、子どもたちは一目散に縁側から次々と家の中へ………。
一気にバケツの水を逆様にしたような土砂降りの雨が、それと同時にピカピカドドン雷鳴があちこちを走り回ります。子どもたちは、皆蚊帳の中に縁側の障子を閉めて息をひそめます。
雷様は親から、そして目上の姉さんや兄さんから臍を取りに来ると伝え聞いていたからです。雷様は、背中に太鼓を持った雷神が光る太鼓を打ち鳴らしながら、真っ黒い雲の中を走りまわって、隙あらば臍を出している子どもたちの臍を取って食べてしまうのかと、小さな頭の中で想像し思いを巡らせていました。雷鳴が鳴るたびに子どもたちは、蚊帳の中で身を寄せ合って耳をふさいで過ぎ去ってゆくのを待っていました。やがて、雷鳴が遠のき明るい青空が見え始めた時、子どもたちは障子をあけて、蚊帳の中からまだ去りやらぬ遠い雷鳴を聞きながら、時折り光る雷鳴に臍を手で押さえながら無事であった臍に安堵するのでした。
すっかり夕立の止んだ庭はひんやりと涼しく、蚊帳の中からぞろぞろと子どもたちは、ランニングシャツからはみ出した黒い腕をなでながら庭へ下りてきます。もうすぐ夕暮れ、澄んだ空気の中に遥か遠く入道雲が去ってゆきます。何処からか味噌汁の匂いが………。子どもたちはちりぢり、母の臍の緒の匂いのする家々に帰ってゆきます。
食べる
死の恐怖に戦い疲れて
残っているのは
生きる人間の本能
何とか食べなければ
食べ物にむきになる
息子に 人のものを食べたと言う
睨んだその目が悲しい
今日も戦っているのか
全てを拒否しながらも
本日もあれこれと食べ物を注文する
頭にあるのは生きるという食べ物だけ
子らに囲まれている母
愛よりも 癒しよりも
生きる 食い物が欲しい
母がひとり居る